修了生の記事
SSAで学んだ方々が様々な分野で活躍しています。SSAを受講した目的、SSAで学んだ知識・スキルやネットワークの活用などについて、修了生の声をご紹介します。
■第2期生
■第4期生
■第5期生
修了生の声

- 株式会社ケイエスピー
インキュベート・投資事業部 - 中村 瑞穂(第2期生)
SSA受講の目的や狙い
【サイエンスパークで創業期支援もできることを目指し、SSAへ】
企業や研究機関が集まる「かながわサイエンスパーク」を運営している株式会社ケイエスピーで、入居している企業への支援業務を担当していました。その一環で、創業期の支援や、もう一歩踏み込んだ経営改善にも取り組みたいと考えるようになり、SSAに応募しました。
入社後6年間は広報業務やイベント事業に従事してきました。その後にサイエンスパークに入居している企業への支援を担当するようになりましたが、充分な支援をできるようになるには知識が不足していると感じていました。
SSAに参加すれば必要な知識を習得することができ、さらには自社において企業の資金調達や販路開拓、専門家・専門サービスの紹介等の事業運営をサポートする役職に就くために必要なスキルを得ることや、実務経験を積むこともできると考えました。
印象に残っているプログラム
【知識だけでなく、グループワークや調整力も会得】
SSAに参加を前にして、グループワークや座学研修を通じて多くの参加者と切磋琢磨し合いながら学び、修了後に企業を支援していく過程でもつながりを持てることを期待していました。
実際に参加してみて、こうした期待通りの経験が得られました。例えば、指数関数的なテクノロジーの成長を前提としてビジネスについて考える「エクスポネンシャル・テクノロジー思考論」の講座では、大変活発なグループワークができました。
また、NEDOが起業家や起業に関心を持っている人たちを対象に実施している「NEDO Technology Commercialization Program」(TCP)では、企業へのメンタリング支援から刺激を受けました。チームごとに会場や日程を決める必要もあり、外部の関係者も交えて調整する力も身についたと感じています。
受講前後でマインドセットや行動の変化
【起業家の支援、「説得力に欠ける」自らもビジネススクールに参加】
SSAでは、事業計画を作ることや、自分のやりたいことを言語化することの難しさに直面している起業家の姿を、間近で目の当たりにしました。この経験を経て、「起業家に伴走し、起業家に頼られるようになりたいと思っているのに、そうした起業家の苦労や思いを自分が体験しないことには説得力に欠けるのではないか」と思うようになりました。
そこでビジネススクールを受講して、自ら新規事業のプランを描いてみました。自分がやりたいことや、実現したい未来を描くことはできました。しかし実際には、自分が思い描いた事業・サービスが社会でどのくらい必要とされているかを、ヒアリング等の方法で確認しなければなりません。自分一人でビジネスはできないことを痛感させられました。
起業家が日々経験していることの一端を体験したのみですが、あらためて起業家への尊敬の念を抱きました。その一方で、一人で起業はできないからこそ、起業家にとって心強い存在でありたいという思いを新たにしました。
SSAで学んだ知識・スキルやネットワークの活用
【技術シーズの目利きを発揮し、ベンチャー支援へ】

最近はサイエンスパーク内にコワーキング&シェアオフィスを開設したところ、SSAで起業の支援を担当したチームに入居いただきました。SSAの修了後も近しい関係でいられることを大変嬉しく思っています。
SSAの修了後は、当初目標としていた通り、企業の資金調達や販路開拓、専門家・専門サービスの紹介等の事業運営をサポートする自社の役職に就くことができました。今後は技術シーズを支援していきながら、将来有望なベンチャー企業が輩出するように貢献できるような人材になりたいと思います。SSAでは事業に結びつく技術シーズを選び出す「目利き力」を得られましたので、今後発揮していくように努めます。

- パーソルベンチャーパートナーズ合同会社
- 岩松 琢磨(第4期生)
SSA受講の目的や狙い
【目指すは研究シーズの事業化 実践の場を求めて受講】
ディープテック・スタートアップの創出・育成に役立つスキルや経験を得ること、人脈をつくることを求めて、SSAを受講しました。
以前から、ビジネスへの発展が期待される研究シーズと、ビジネススクールに通っている経営人材をマッチングさせることを目指した支援活動を行ってきました。しかし、実際にマッチングが成立する段階にはなかなか至らず、研究シーズを支援する経験を積めないままでいました。
そうした中で、自らが運営に携わっているビジネスケースのコンペティションをNEDOが後援していた縁で、関係者からSSAを紹介されたことが受講のきっかけでした。プログラムを見てみると、ディープテックに関する講義や、スタートアップを支援している起業家によるメンタリングにOJTとして参加できること、事業化支援人材(事業カタライザー)やSSA受講生とのネットワークをつくることができることが分かりました。研究シーズの支援を実践できる点に魅力を感じ、受講を決意しました。
印象に残っているプログラム
【社会実装に必要なのは、パッションと再現性のある仕組み】
受講して、特に印象に残った講座は「科学技術ビジネスプロデュース論」でした。講師は、リバネスで代表取締役・グループCEOを務める丸幸弘さん。2005年に世界で初めてミドリムシの食用屋外大量培養技術の確立に成功した株式会社ユーグレナに対して、設立や同技術の事業化をサポートした経験や、ベンチャー・キャピタル(VC)として投資をした経験を聞きました。研究シーズとの向き合い方、特にディープイシュー(根深い課題)を解決したいというパッションと、ディープテック・スタートアップにおいて再現性がある仕組みをつくろうとする姿勢は、研究シーズの社会実装を推進していくことを模索していた私に深く刺さりました。
受講前後でマインドセットや行動の変化
【プレシード期の事業化・人材確保の支援へ】
SSAでの学びを経て、創業前後のプレシード期における事業化や人材の確保・定着に向けた支援の必要性を特に強く感じ、そのための行動が増えました。
国内のディープテック・スタートアップでは、研究シーズを所有している研究者が自ら起業するケースが多い状況にあります。私自身も過去には研究者として同じ経験をしましたが、研究者にとってビジネスへの初挑戦は難易度が高いものです。SSAでスタートアップへのメンタリングを経験して、そのことを再認識させられました。さらに研究者自身が起業することで、研究に注力する人材が不足し、事業化に向けた研究活動や新しい研究シーズが不足してしまいます。こうしたプレシード期の課題から、より多くのディープテック・スタートアップを設立することを目指すためには、研究者による事業化を支援することと、経営人材の参画が必要不可欠です。この2つの領域で支援活動をより活性化させていきたいと考えて取り組むようになりました。
SSAで学んだ知識・スキルやネットワークの活用
【受講生ネットワークによって実現したアイデアソン】

そして、受講生間のネットワークを築くことができたことが、SSAの受講を通じて得られた最も大きな収穫でした。私は現在も研究シーズと経営人材のマッチングに取り組んでいますが、以前とは異なるのが、受講生のネットワークを通じてディープテック・スタートアップや研究シーズの情報を共有していることです。
この取り組みが結実した一例として、理化学研究所(理研)の研究成果を社会実装することを目的としている株式会社理研鼎業に所属している同期生と協力して開催した、コラボレーションイベントがあります。理研に研究シーズを提供してもらい、一方でビジネススクールに通う経営人材にイベントへ参加してもらって、参加者が理研の研究シーズを題材として事業化のアイデアを競うアイデアソンを開催しました。さらに、提案されたアイデアを事業として実現することを目指しました。研究者とマッチングできたチームは翌年、国立研究開発法人科学技術振興機構がスタートアップを支援するために設けている補助金にも採択され、事業内容をさらに深めています。
今後もこのようなマッチングイベントを企画して、より多くの研究シーズを事業化するための場にしたいと考えています。
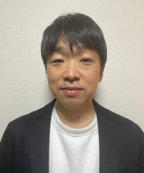
- 合同会社カケル
代表社員 - 北沢 裕人(第4期生)
SSA受講の目的や狙い
【スタートアップの支援側も「アップデート」】
事業会社による新規事業や創業期のスタートアップを支援するために必要な知識や経験を深めること、人的ネットワークを広げることを目指して、SSAを受講しました。
これまで自らの会社でスタートアップ等を支援する事業を行ってきました。支援では、過去に私自身が事業会社やスタートアップで事業の企画立案・推進、組織体制の構築などを経験してきたことによる知見を活用していました。ただ、支援する立場としては、それでも知識・経験の不足や人脈の狭さを課題と捉えており、今以上の支援を行うには自分自身を大きく「アップデート」する必要性を感じていました。加えて、こうした支援事業を行っている自分自身のミッションがはっきりとしていないことにも課題があると感じていました。
そうしたタイミングでSSAの募集を知った時には、まさに自分が求めている場に出会うことができたと感じられました。その日のうちに応募しました。
印象に残っているプログラム
【OJTではスタートアップへのメンタリングも】
特に印象に残った講座はOn the Job Training(OJT)研修です。NEDOが実施する研究開発型スタートアップ向けの助成事業「NEP」における、スタートアップに対するメンタリングや、スタートアップのピッチイベントに参加しました。
自分自身の経験から、新規事業やスタートアップを立ち上げていく過程における、当事者の苦しみや喜びはよくわかっていました。一方で、支援者に必要とされる体系的な知識や、スタートアップに対する心構えや接し方などの姿勢は、メンタリング等のOJTを通じて得られたことが多くありました。
また、SSA全体を通じて、スタートアップ支援の経験が豊富な講師の方々から経験や支援における考え方を聞くことからも、同様の知見を得られました。
受講前後でマインドセットや行動の変化
【「対症療法」から「自走」支援へ】
こうした知見を得られただけでなく、気づかされたことがありました。それは、これまで私が行ってきたスタートアップへの支援が「対症療法」であったことです。
支援では、収益性などの自社の都合や、自らの事業経験などを考慮して、自分自身が手を動かして事業を推進する姿勢をとってきました。それでも事業は前進し、スタートアップの成長にもつながるので、メリットはあります。しかしそれだけでは、支援を終えて自分がそのスタートアップを離れた後に、残せるものが少ないことにSSAの受講を通じて気づかされました。
OJTとしてNEPによるメンタリングに加わる中で、支援を受けた企業が自走していくようになった姿を見ることができました。そのことが大きく影響して、支援では自分が手を動かすだけでなく、支援対象の企業が自走していくことができる体制を築くことを目指していくべきであるという、新たなミッションを定めることができました。
SSAで学んだ知識・スキルやネットワークの活用
【スタートアップを見守る立場、共同で事業を推進する立場を切り替えられるように】

現在は支援の中で、相手の企業が自走していくことができるように一歩引いて見守る立場と、自らも加わりながら事業を推進していく立場の切り替えを意識して、企業とコミュニケーションをとっています。支援対象の企業にとっても、自分たちが取り組むべきである物事と、支援者である私を活用する物事の線引きが明確になったことで、よりよい関係を得られるようになったと思います。
SSAの受講や、学んだ内容を活かした事業の取組みを踏まえて、これまで取り組んできたスタートアップなどの事業支援活動の他にも新たな領域に乗り出そうとしています。1つは、地方に不足しているスタートアップのビジネスエコシステムの構築支援です。もう1つは、SSA修了生のネットワーキングや、継続的な知識習得・スキル向上の支援、ディープテックのシーズ化・事業化の支援に取り組んでいくことです。こうした活動のために、新たな一般社団法人も立ち上げました。

- つくば市 政策イノベーション部
スタートアップ推進室長 - 屋代 知行(第4期生)
SSA受講の目的や狙い
【スタートアップと支援機関 自治体が橋渡し役】
私が勤めている茨城県つくば市は、事業に発展しそうな技術シーズを有している研究機関と、スタートアップを支援する金融機関などをマッチングさせる橋渡し役を担っています。研究開発型のスタートアップとコミュニケーションを深めていきたいと考えたことが、SSAに応募した理由です。
つくば市にある「筑波研究学園都市」は、官民合わせて約150の研究機関が集まっており、約2万人の研究従事者が活動しています。つくばエクスプレス開業を契機に、人口は右肩上がりに増えています。
しかし、街がこの先も持続的に発展していくためには、つくば市の特性を生かして産業が根付くことが必要です。その一つとして、ディープテックから生まれるスタートアップに着目し、支援をしています。
印象に残っているプログラム
【スタートアップと大企業の提携、新たな選択肢に】
SSAでは、研究開発型のスタートアップが成長していった事例や、基本的な支援の内容を学ぶことができました。
印象に残っている講座に、一橋大学の青島矢一教授による「イノベーション論」があります。過去の事例分析により、イノベーションには「時間資源」、「人的資源」、「金銭的資源」の三つを投入することが欠かせないこと、大企業はこうした資源を投入することが可能であることが紹介されました。
研究開発型スタートアップを支援する立場からすると、イノベーションの創出に向けて大企業とスタートアップが業務提携していくことの可能性を感じられ、今後の支援における方法を考えるうえで選択肢の一つになりました。
受講前後でマインドセットや行動の変化
【「ディープテックが国内外の社会問題を解決する」というマインド】
つくば市によるスタートアップ支援の姿勢はもちろんですが、SSAを修了してからは、NEDOのミッションである「エネルギー・地球環境問題の解決」「産業技術力の強化」「イノベーション・アクセラレーターとしてのマネジメント」も意識するようになりました。具体的には支援のなかで、筑波研究学園都市で生まれたディープテックが国内外の社会問題の解決につながることを心掛けるようになりました。こうしたマインドを持って研究開発型のスタートアップとコミュニケーションをとっていくことは、スタートアップの成長にもつながると思っています。
SSAで学んだ知識・スキルやネットワークの活用
【講師、フェローとのつながりがサポートの支えに】

SSAを修了したことによる財産の一つが、講師の方々とのつながりです。研究開発型スタートアップを支援するうえで一番のポイントは、技術の開発に時間を要するためベンチャーキャピタルからの出資が受けにくい点にあります。この特性を踏まえて支援していくためには、NEDOによるスタートアップの支援事業や、政府の「日本版SBIR」などの外部資金を活用することが欠かせません。そのためには、SSA講師の方々とネットワークを築いて情報を日々交換していくことが、スタートアップをサポートするうえでの支えとなります。
そして何よりも、行政マンでありながらSSAフェローという経歴を持つことで、研究機関や支援機関等からの信頼感が高まったと感じています。研究開発型スタートアップの手によりディープテックの社会実装が進んでいく中で、NEDOなどの国立研究開発法人による事業を適切なタイミングで活用したり、支援機関や行政による連携・サポートを進めたりする成功事例を、つくば市で出していくことが大切だと考えています。

- 日揮株式会社 未来戦略室
マネージャー - 坂本 惇(第5期生)
SSA受講の目的や狙い
【個人の知見、独学には限界 門戸を開くきっかけに】
研究開発型スタートアップを支援する手法や、国内のスタートアップ・エコシステム全体の発展に寄与できる方法を学びたいと考え、SSAに応募しました。
きっかけは、所属する日揮株式会社でコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)を立ち上げて、シード、アーリーステージの研究開発型スタートアップ等との事業共創や投資先への伴走支援を開始したことでした。それまでに培ってきた知見や経験をもとにアクションをとってきましたが、研究開発型スタートアップは専門性が高く、それぞれに固有かつ困難な課題に取り組んでおり、個人の知見や独学に基づいて支援することに限界を感じるようになりました。
特に、起業家の考えと事業の本質を適切にとらえて、より発展させていくことができる前向きな連携ができるように、従来の支援を変えていく方法がないかという、正解のない問いに悶々と悩んでいました。
印象に残っているプログラム
【講師の血が通ったメンタリングで「目が覚めた」】
参加して、印象に残った講座が「研究開発型ベンチャーのメンタリング(概論)」でした。
講師の尾崎典明さん(S-factory代表、筑波大学客員教授)による起業家へのメンタリングは、事実であれば厳しい内容であったとしても適切に伝え、そのうえで起業家が目指すビジョンをどのように達成できるか考える「壁打ち役」にもなるものでした。血が通ったメンタリングは、まさに起業家の伴走者と呼ぶべき振る舞いでした。
SSAに参加するまでは、自分のメンタリングの経験や知見を通して、メンターのあるべき姿を想像できているつもりでいました。しかし、こうしたメンタリングを直に見聞きできたことは、短い時間でありながらも目の覚める経験となりました。
受講前後でマインドセットや行動の変化
【表面的な理解ではなく、ビジョンを実現できるように】
受講前は、まずはスタートアップ支援に必要な知識を学ぶことが、メンタリングに効果的であると考えていました。一方でSSAのプログラムを振り返ると、体系的な知識の獲得だけでなく、起業家の内面にある想いを具体的な言葉や計画に落とし込んでいくことに協力することの重要性に気付かされました。
プログラムのなかで講師や同期、起業家と密に議論することを通じて、自分が社会に対して「何を貢献したいのか」、「何を貢献できるのか」と内省したことで、事業の表面的な理解ではなく起業家の内面に踏み込むことの必要性に思い至りました。
受講後は、起業家のビジョンに共感しながら、実現できるよう具体的な手段や事業に落とし込むようにしています。起業家に対するリスペクトはさらに高まり、表層的ではない議論を持ち掛けるようになったと感じています。
SSAで学んだ知識・スキルやネットワークの活用
【SSAネットワークによって、支援者の孤独感から解放】

スタートアップ支援については元々、「起業家だけではなく、支援者も実は孤独になりがちなのではないか」という思いがありました。起業家の壁打ち相手を務める際、特に研究開発型スタートアップの起業家との議論では、幅広い経営知識と深い技術領域の知識をいずれもアップデートしていくことが常に求められるためです。
以前はこうしたアップデートの方法が、独力で努力できる範囲に限られていました。しかし、SSAを通じて起業や経営に関してベースとなる知識を学ぶことができ、さらに講師や同期、NEDOと強いネットワークを形成できたことにより、支援者として感じていた孤独感からは解放されました。
現在はファンドや事業開発の活動のなかで、スタートアップの経営者と議論する機会が増えています。そのような時には、所属元における「投資担当」、「事業開発担当」、「経営企画担当」という立場と、純粋なスタートアップの支援者という、4つの顔を切り替えながら思考するようにしています。すべての企業への投資や連携は現実的に不可能ですが、それでもご縁ができた起業家に対して、血が通う一個人としてできる事が少しでもないかと検討するよう心掛けています。

- アステラス製薬株式会社
創薬アクセレレーター創薬アイディエーショングループ - 藤本 有美(第5期生)
SSA受講の目的や狙い
【社内研究者の支援、経験不足を補うためSSAを活用】
SSAを受講したきっかけとなったのは、勤め先の製薬会社でエコシステムの構築や社内スタートアップの仕組みづくりを行っている部署に飛び込んだことでした。
それまでは研究職や、初期の事業開発に必要な契約関連の仕事をしていました。しかし、持続的かつ革新的なイノベーションを生み出すためには、研究員が新たな取り組みをできるようになるための支援や仕組みづくりが必要だと感じたため、新しい組織に希望して加わりました。
ただ、スタートアップ支援に関する経験がなく、他社での勤務経験もなかったため、社外で活動することや経験豊富な方々から学ぶことの必要性を強く感じ、SSAを受講しました。
印象に残っているプログラム
【講師から学んだ「支援者の心得」】
SSAで各講師から教わった支援者の心得は、今でも心に刻んでいます。
受講する前は、アイデアや事業計画をより良くしようとすることばかりにフォーカスして、研究者に対して一方的なコメントになりがちでした。そうした中で、講師の尾崎典明さん(S-factory代表、筑波大学客員教授)から、まずは相手が何を成し得たいのか、本当に望んでいることは何かを紐解いていき、その上で相手が納得する最良のアクションに導いていく手順を教わりました。
また、講師の曽我弘さん(株式会社カピオン代表取締役)がおっしゃるように、多忙な起業家の時間を割いている自覚を持って、彼らに有益となるよう働けているかを常に意識するようになりました。
さらに山形県鶴岡市で開催された合宿では、慶応義塾大学の冨田勝教授からイノベーションが生まれる環境とはどのようなものなのかを紹介いただきました。講演を通じて、おもしろいことをやりたいと思う気持ちと、それを受け入れて応援する周りにいる人たちの熱意の重要性をあらためて感じました。
受講前後でマインドセットや行動の変化
【学んだことは自信に、他の受講生からの刺激は情熱につながった】
SSAを受講する前は社内でも少人数で活動していたことから、支援に対するジレンマを感じたり、社内の周囲に対して閉鎖的になっていたりしました。そこからSSAでの学びを経て、支援の重要性を再認識し、自信を深めることができました。
具体的には、講師の方々をはじめ、活躍されている多くの有識者の方々による講義を通じてたくさんの知識や考えを知ることができたことが、自信を養うことにつながりました。そして何よりも、他の受講生などさまざまなケーパビリティや立場でありながら同じ志を持つ多くの仲間と出会い、刺激を受けたことで、支援者としての情熱が高まりました。
SSAで学んだ知識・スキルやネットワークの活用
【体得したマインドセットや心構え 企画運営等の推進力に】

SSAで得た知識やスキル、ネットワークを活かす機会は、これまでに多々ありました。その一つが、講師の一人をお招きして、イノベーション創出に必要なマインドセットやビジネススキルを社内の希望者に対して3日間にわたり講義していただいたことです。自分自身がスタートアップ創出にはどのようなマインドセットや視点が必要かを理解していたことで、スムーズにワークショップの企画を進めることができました。
また、教わった支援者の心得を踏まえて研究員を支援する際の心構えやスタイルをアップデートできたほか、学んだ幅広い知識を下地にして説得力を持ったメッセージを発信できるようになりました。こうした変化は、各種イベントや仕組みの構築において非常に役立ちました。
今後も社内、そして日本で継続的にイノベーションが生まれるように、SSAで知り合った方々とのネットワークを大切にしながらライフサイエンスのエコシステムに貢献していきたいと思っています。
最終更新日:2025年7月16日
