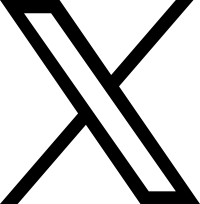治療用アプリと治験を効率化するブロックチェーン技術で少子化が進む日本の医療をサポート/サスメド株式会社
サスメド株式会社は、社名(Sustainable Medicine)が表す通り、「持続可能な医療」を目指して立ち上げられたスタートアップ企業です。主な事業は、不眠症や乳がん、腎臓病などの患者さんに向けた「治療用アプリ」の開発と、ブロックチェーン技術で臨床試験の効率化を推進する「サスメドシステム」の2つ。
同社のようなディープテック企業はアカデミアが出自の人が多く、起業にあたっては知財やファイナンスに課題を持つケースが少なくありません。規制が厳しい医療業界で、どのようにNEDOを活用し、課題を解決してきたのか、同社代表取締役社長の上野太郎氏にお話を聞きました。
 左)サスメド株式会社代表取締役社長 上野 太郎さん
左)サスメド株式会社代表取締役社長 上野 太郎さん
右)NEDOイノベーション推進部長 吉田 剛
- 「保険適用される」治療用アプリの開発
- 規制が強い医療業界でスタートアップを立ち上げるまで
- ブロックチェーンの技術には優れるが「規格化」で遅れをとっている日本
- 少子化が見えている今後の日本の医療は効率化とインフラで支えるべき
- NEDOで知財やファイナンスの重要性を早期に学べたのは大きかった
- 沿革とNEDOプロジェクトの歩み
「保険適用される」治療用アプリの開発
吉田) まず、貴社の事業概要やビジネスモデルについてお聞かせいただけますか。
上野さん) 不眠症などの治療用のアプリを医療機器として開発しています。ヘルスケアではなく、医療産業の中で承認いただくものとして開発していることがポイントです。もう一点、治験の課題に対するブロックチェーンの活用についても、NEDOの支援をいただきながらチャレンジしています。
吉田) 治療用アプリは、どのようなビジネスモデルとなるのですか。
上野さん) 医薬品や医療機器と同じです。私共は医療機器の製造販売業として、医療機関に対してアプリを提供します。そして、基本的には医師が患者さんに対して治療行為としてアプリを「処方」します。ですから、お金の流れとしては患者さんが自己負担で3割を支払い、残りの7割については保険者から支払われます。その医療機関の収益からアプリの費用をいただくというモデルです。
吉田) 医療ビジネスは、保険適用がなされるのか否かが重要と考えます。治療用アプリについてはアメリカで先行例があったため、日本でもそれが認められるという読みで開発されたのですか。
上野さん) はい、もともと2014年の時点でアプリ単体でも医療機器になるということは、薬機法の改正で規定されていました。ただ、アプリに対して保険点数の枠が作られたのは、実は2022年の診療報酬改定です。
吉田) ソフトウェアが医療機器として認められたこと自体が画期的だと思います。貴社を含む日本の治療用アプリに関わる複数企業が、2019年に「日本デジタルセラピューティクス推進研究会」という組織を作られていますね。
上野さん) 今は「日本デジタルヘルス・アライアンス(JaDHA)」という組織になっています。治療用アプリに注目する事業者が、研究会という形で立ち上げたものです。
吉田) そこでの議論や研究成果は厚生労働省にフィードバックされているのですか。
上野さん) はい、例えば「海外ではこうした産業が既に立ち上がっている」といった情報をフィードバックさせていただいています。
規制が強い医療業界でスタートアップを立ち上げるまで
吉田)上野さんは、薬機法のハードルがなく比較的早めに収益を上げられるヘルスケア事業と、治療用アプリという医療機器の2つの可能性があったと思います。後者に絞っていくことは、お一人で決断されたのですか。出資者によっては「まずキャッシュポイントありき」という話もあったと思うのですが。
上野さん) NEDO TCP(起業意識のある研究者等を支援するためのプログラム)の研修では「あったらいいな(Nice to have)ではダメです。無いと困る(Must to have)ものを作りましょう」という言葉が印象に残っています。投資家を選ぶ際も、早期にマネタイズできる事業を求めるベンチャーキャピタルもある中で、現在のパートナーからは「ディープテックで社会的インパクトのあることをやりましょう」と言ってもらえました。
吉田)医療分野は規制が強く、スタートアップのハードルは高いと思うのですが、どのように対応されたのでしょうか。お話を伺っていると、ネットワークの広げ方がうまいとの印象です。
上野さん)そうですね、例えば薬事については、製薬メーカーで治験業務を経験してきたメンバーが弊社にジョインしてくれています。社外アドバイザーについても、私共のビジョンを理解いただいた上で、多くの方に助けていただいています。
吉田)NEDOとしては、デジタル医療のトップランナーの皆さんを採択できて良かったと思っています。
上野さん)NEDOにつきましては、先ほど触れたTCPに始まり、SUI(企業化可能性調査等の実施)、STS(シード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化支援) 、SCA(企業間連携スタートアップに対する事業化支援)とフル活用させていただいています。NEDOがなかったら、弊社は今の状態ではなかったでしょう。
吉田)NEDOとしては「補助金で経営者が研究に専念できる」「資金集めに奔走しなくて済む」という部分はアピールしていきたいです。補助金のメリットについては、どのように感じておられますか。
上野さん) 起業時を振り返ると、まだディープテックはベンチャーキャピタルも手を出したがらない分野で、資金調達の選択肢もさほどありませんでした。その中でNEDOの補助金をいただくことで、研究開発を深掘っていくことができたと思っています。
ブロックチェーンの技術には優れるが「規格化」で遅れをとっている日本
吉田)貴社の主事業の一つであるブロックチェーンについては、医療データという個人情報を安全にやりとりすることがポイントだと考えます。
上野さん)そうですね。今の治験にはデータの利益相反が起こりえると認識しています。製薬企業が依頼して治験を行い、そのデータをもとに承認申請をするため、当然ながら良い結果が出れば製薬企業に利益を生みますし、データ改ざんの事例も過去に存在します。ですから、現在は多くの工数をかけてデータの真正性を担保しているわけです。私共も治験をやる中でそのハードルが高いと感じ、ブロックチェーンで効率化できないかというのが、そもそものアイデアです。
吉田)私は10年ほど前にインドにいたのですが、2010年ぐらいにインドはマイナンバーを始めて、直近ではそこに医療のデータをつなげるという話も出ています。日本の医療もデジタル化していく中で、貴社のブロックチェーン技術が求められるのではないでしょうか。
上野さん)おっしゃる通り、インドではインフラがない中にスマホが入って、一気にデジタル化が進んでいます。一方、日本の医療はある程度のシステムができてしまっているので、その上に労働集約的な対応をしてしまって、結果としてデジタル化が遅れているように感じています。
吉田)その辺りの状況について、もう少し詳しく教えていただけますか。
上野さん)治療用アプリについては欧米の方が進んでいます。ブロックチェーンの治療応用については、実は規制緩和まで踏み込んで成果が出ていたという意味では日本がリードしていました。内閣府の方々と取り組んだ成果が、EUのイノベーションプログラムであるHorizon Europeのレポートで論拠として参照されています。一方で、日本が弱いと思うのは「規格化」です。その点はヨーロッパのISO(国際標準化機構)が上手で、様々な分野で持っていかれてしまっているという状況です。日本でブロックチェーンの社会実装がなかなか進まないことについては、危機感を持っています。
少子化が見えている今後の日本の医療は効率化とインフラで支えるべき
吉田)スタートアップはチームビルディングに苦労するところが多いように感じます。特に貴社の場合はアプリにおける治療の継続性が重要で、これを実装できるエンジニアはなかなかいないと思うのですが。
上野さん)弊社のCTOはわりと名が知れているスキルの高いエンジニアですが、「技術が人の健康や命に貢献できる」という理念に共感してもらい、ジョインしてくれています。
吉田)アカデミア出自の方が多いということで、皆さんは論文も書かれるのですか。
上野さん)はい、私共は今までに複数の論文を発表しています。いま海外ではブロックチェーンの医療運用に関する論文が急増していますが、省庁と連携して、規制緩和につなげるところまでやったという点では、日本の方がエッジは立っていると思っています。
吉田)あとは具体的な応用ですよね。先ほどのお話にもありましたが、病院か製薬会社なのか、どこかもう一つスイッチを押さないと動いていかないところなのですか。
上野さん)そうですね。やはりブロックチェーンの社会実装に関する課題には、インセンティブの設計が重要になってきます。
吉田)日本は医師の働き方改革(2024年4月からの残業規制)、2025年問題(団塊の世代が後期高齢者となる75歳に達し、医療や介護などの社会保障費の急増が懸念される問題)があるところで、何とか下支えができればと思っているのですが。それを含めた医療のデジタル化の未来について伺えますか。
上野さん)おっしゃる通り、少子化が決まっている中で日本の医療をどう支えるかというときは、頭数で支えるのではなく、インフラとしてシステム化していくことが重要だと思います。
NEDOで知財やファイナンスの重要性を早期に学べたのは大きかった
吉田) このコーナーの読者は多くが研究開発型スタートアップで、起業前・起業直後と思うのですが、後続のスタートアップのために「初期段階でこれをやっておくべき」といったアドバイスがありましたら、お願いします。
上野さん) 知財戦略と資本政策ですね、そうした部分は後戻りできないので、早くから重要性を分かっておく必要があると思います。私はTCPの研修で知財やファイナンスの大切さを学ばせていただいたとことが、ありがたかったです。
吉田) ただ実地となると、またハードル上がりますよね。そこはアドバイザーに具体的に相談しなければなりませんから。
上野さん) はい、知識だけで動いているわけではないです。私もベンチャーを経営する中で、本から学ぶことはありますが、その時は「ふうん」と思っても、やはり課題に直面しないと「そういうことだったのか」と肚に落ちない部分はあります。そうした際に相談できる人のネットワークを広げていくのは重要だと思います。
吉田) 資本政策について相談相手を見つけるのはなかなか難しいと思います。いきなりベンチャーキャピタルに相談するわけにもいきませんからね。どのようなアドバイザーを、どう見つけたのですか。
上野さん) NEDOのネットワークにはいろいろな人がいるので、多くの人のお話が聞けたのはありがたかったです。特に私共は、元々アカデミアの身分を捨てて社会実装のためにリスクを取ってやっています。投資する側がこちらの姿勢を理解してくれるかどうかは、重要でした。
吉田) 今後、ビジネスのポートフォリオはどのようになっていきますか。
上野さん) 不眠症の治療用アプリは現在承認申請をしていますので、認可されればそこから売り上げが立っていきます。一方のブロックチェーンについては、もうシステム自体はできていて規制もクリアしていますので、あとはいかに活用事例を増やしていくかというステータスです。
吉田) 例えば貴社が海外のマーケットを狙いにいく際は、NEDOは海外実証や補助金などいろいろなツールを持っていますので、何かしらお手伝いできると思います。
上野さん) ぜひ。私共は小さな組織なので、そうした部分でサポートいただけると非常にありがたいです。
吉田) 先ほども申しました通り、日本の少子高齢化、医療の問題は深刻ですから、そこに対する貴社の貢献に期待しています。引き続き頑張っていただければと思います。
上野さん) ありがとうございます。よろしくお願いします。
沿革とNEDOプロジェクトの歩み
| サスメド沿革 | NEDOプロジェクト | |
|---|---|---|
| 2015年7月 | 東京都文京区においてサスメド合同会社を設立 | |
| 2015年10月 | 起業家の育成支援プログラムTCPに採択 | |
| 2016年2月 | 株式会社に組織変更 | |
| 2016年3月 | 起業家候補(SUI)プログラムに採択 0.34億円 | |
| 2016年9月 | 不眠障害治療用アプリの臨床試験を国内2施設で開始 | |
| 2016年12月 | Beyond Next Ventures株式会社を引受先とする約7,000万円の第三者割当増資を実施 | |
| 2017年4月 | シード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化支援(STS採択)0.3億円 | |
| 2017年8月 | 本社移転(中央区日本橋) | |
| 2018年3月、6月 | 複数社を引受先とする約7.2億円の第三者割当増資を実施 | |
| 2018年6月 | ブロックチェーン技術を用いた臨床開発支援システムの実証試験を開始 | |
| 2018年11月 | 企業間連携スタートアップに対する事業化支援プログラム(SCA)に採択 1.0億円 | |
| 2019年7月 | 経済産業省、JETRO、NEDOによるスタートアップ支援プログラム「J-Startup」に選定 | |
| AIに関する技術開発事業に採択 0.36億円 | ||
| 2019年12月 | 本社移転(中央区日本橋) | |
| 2020年4月 | 国立研究開発法人国立がん研究センターとの共同研究が厚生労働科学研究費(がん対策推進総合研究事業)に採択 | |
| 2020年7月 | AIに関する技術開発事業に採択 1.6億円 | |
| 2020年8-12月 | 複数社を引受先とする約15億円の第三者割当増資を実施 | |
| 2021年10月 | 本社移転 | |
| 2021年12月 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 | |
| 塩野義製薬株式会社と不眠症害治療用アプリの販売提携契約を締結 |
最終更新日:2022年8月29日